「絶対音感あるんですか?」演奏家や作曲家にそう聞きたい人もいるだろう。かつての私もそうだった。
のちに夫になる人にそう聞いた時の、まるで濡れ雑巾を見るような眼差しを私は決して忘れないだろう。
その時、彼は冷ややかにこう言った。「相対音感はあるけど?」と。
彼は鳴っている音が何かをすぐに言い当てることができる。いくつもの音が一緒であっても。それなのに絶対音感は持っていないという。
絶対音感、相対音感とは何か。そして音楽家に絶対音感ありますかと聞いてはいけないワケとは。
「ハッピーバースデイの歌」は、毎回決まったピッチで歌われるわけではない。どのピッチから歌い始められても、音程(相対音高)が正しく歌われる限りは、「ハッピーバースデイの歌」であることに変わりはなく、絶対音感がない普通の人はそれを何もおかしいと感じることはない。それをおかしいと感じて一緒に歌うことができないことさえあるのは、融通のきかない絶対音感の持ち主だけだ。音楽をする(聴く)うえで、絶対音感はなくてもよい(ときにはないほうがよい)が、相対音感はなくてはならないものである。
『絶対音感神話』宮崎謙一 著
絶対音感は天才的才能?
絶対音感について一般的によく知られているのは、「身の回りの音がなんでもドレミで聴こえる」という逸話だろう。
救急車のサイレンも、スズメの鳴き声もドレミファソラシドで聞こえてしまうらしい。
絶対音感の技を披露などと言って、初めて聞くピアノの曲を(もちろん両手の演奏で)、一つも間違わないで楽譜に書き起こす人もいる。
実際にテレビや雑誌に出てくる音楽家がこうした能力を披露していると、やはり一流の音楽家は絶対音感が必要なのだという印象を持ってしまう。
絶対音感とは
440ヘルツの周波数は、それが(440ヘルツ平均律で調律されている場合の)ピアノでいうところの「真ん中より少し右のラ」である。絶対音感を持つ人は、440ヘルツを聞くとすぐにそれをラだと答え、495ヘルツを聴くと、それ・・・・・
いや、もうやめた。
ヘルツやら、周波数やら、平均律やら言うからますますわかりにくく、誤解が生じてしまうのだ。
こんな例え話はどうだろう。
優れた色彩感覚を持つ人がいる。ほんの数パーセント薄い、明るいなどと比較してわかるだけでなく、無数にある緑色のバリエーションから一色を見て、
「これは、CMYK100-0-70-30の緑色だね、インドの国旗と同じ。」などと詳しく判別できる。
色に対して何の基準もなくても、すぐさま細かく言い当てられる敏感さ。
絶対音感も、まさにこのような”基準なしで瞬時に識別できる”優れた感覚である。
相対音感とは
さて、作曲家である夫は絶対音感ではなく、相対音感を持っているという。しかし傍目には絶対音感のようにみえる。これはどういうことだろうか。
基準になる音があって、そのどちらが高いか低いかを判別したり、これがドなら、今のはミ、と基準になる音と照らし合わせて識別できる。これが相対音感である。
夫の頭の中には、音叉(おんさ)のようなものがあって、その基準音を思い出して、聞こえる音を識別しているらしい。
音叉というのは、楽器や音響測定の周波数の基準にするための金属の棒で、エヴァンゲリオンに出てくるロンギヌスの槍のような二又の形をしている。
夫は脳内にあるこの基準音装置のような能力を使って、「相対的に音を識別」しているから、絶対音感ではないという。
絶対音感が生まれつき持った感覚の鋭さによるものが大きいことに比べ、相対音感はある程度訓練で得られるとされている。
音楽家にとって必要な音感とは
さて、ではなぜ音楽家に「絶対音感を持っていますか」と聞くべきではないと私が主張するのか。
それは「絶対音感の有無は、音楽家としての力量とは別問題」とわかったからである。
色味を判別できる能力が高かったとしても、センスのよい服をデザインしたり、素敵なイラストを描けるわけではないことは想像できるだろう。
絶対音感もこれと同じである。
この音が何なのかを分かるだけよりも、他の人の楽器や歌声に合わせられ、豊かに調和して演奏できる技術と感性のほうが演奏家には求められている。
絶対的に音を判別できるより、今鳴っている音を相対的に、そして極めて繊細に判断できる能力を磨かなければらないのだ。
「絶対音感ありますか?」と音楽家に聞くことは、そのスキルや表現力を褒めるよりはむしろ、
この色なんだかわかる?とデザイナーに聞くのと同じく、少し「失礼なこと」であるかもしれないのだ。
絶対音感の何たるかは広まらず、そのイメージだけが先行し、あたかも音楽的才能の発露であるかのように捉える。
この誤解と誤用を正しておかないと、私が夫にされたような冷めた眼差しをお見舞いされることになってしまうのである。
絶対音感そのものは、先天的で突出した才能の一部分であることは間違いない。敏捷な感覚を持っていることは、まぎれもなく秀でた才能である。
しかしながら、それは音楽的なこと、演奏能力や作曲能力の高さには必ずしも直結しないのだ。
演奏家は常に相対音感を磨き、より美しいハーモニーを奏でようと努力している。それこそが素晴らしいことであり、音楽家としての力量である。
讃えるべきは絶対音感ではなく、相対音感を磨き続けている、その努力なのだ。
私もできることなら相対音感を身につけたいと思う。もっと自由に、もっと繊細に音楽を楽しめらたらどんなにいいだろう。簡単にできることではないと、分かってはいるけれど。
フィギュアについたロンギヌスの槍をくるくる回しながら、私は今日もまた、そんなことを考えている。

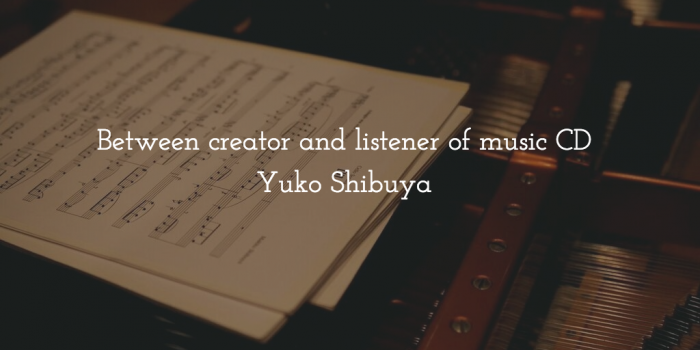


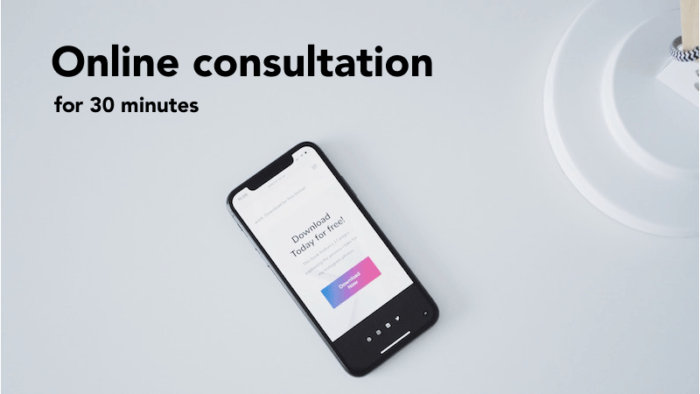


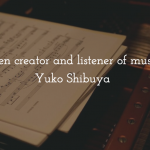
 12
12