著者デビューを果たした作家からよく言われるのが、「毎日見慣れた風景でも、本を出すと、違った風景に見える」ということだ。一読者でいたころは見えなかったものが見えるようになり、その人の見える世界は大きく変わるという。
無名の作家が大ベストセラー作家になる欧米の仕組み
私はもともと、海外作家の翻訳版権を売るエージェント会社、イングリッシュ・エージエンシー・ジャパンに一九九七年から四年間勤務し、そこで欧米の書籍、特に映画の原作やノベライズ作品、ビジネス書、スポーツ関連書の日本語翻訳権を原著者に代わって日本の出版社に売り込む仕事をしていた。
たとえば、ヴインセント・ギャロの『バッファロー66』のノベライズ(B・R・サーカス)やフランシス・F・コッポラの『ゾエトロープ』(角川書店)などを手がけていた。世界のカッコいい文化を輸入しているという感覚があって日々が充実していた。
しかし、ふとしたきっかけから転機が訪れた。
翻訳書籍の業界では年に数回、世界中から翻訳権を売買する人たちが集まるブックフェアが世界各地で開催される。中でもシカゴ、フランクフルト、ロンドンなどのブックフェアは一般の人でも聞いたことがあるだろう。
私は、イングリッシュ・エージェンシーの社員として、毎年それらに参加した。
初めてフランクフルトのブックフェアに行ったときのことだ。私は、欧米と日本の出版システムが大きく違うことに気づいた。欧米では「作家のエージェント(Authors’agent)」システムが定着し、うまく機能していたのである。その結果、無名だけど力量のある新人作家が次から次へと登場していた。
たとえば『ワイルド・スワン』を書いたユン・チアン、『ハリー・ポッター』シリーズのJ・K・ローリング。二人はこの世界的なベストセラーを上梓するまで、まったく実績のない無名の作家だった。
彼女たちのような才能はあるがまったくの新人が作家のエージェントの手によってデビューし、大ベストセラーになるべくしてなっていたのだ。私にはこの欧米の出版システムが、日本よりはるかに進んでいるように思えた。そして、そのシステムが非常にうらやましかった。
エージェントとして、作家の見る景色を変えてみたい
それから私はブックフェアへ赴くたびに、欧米の作家のエージェントたちと交流を深め、情報を集め、意見を交換した。いつかこの事業を日本でも手がけたいと考えた。
そして二〇〇一年十月に、角川書店で編集に携わっていたF君に手伝ってもらい、「作家のエージェント」の会社を興したのである。六本木の、たった九坪の小さなオフィス。自分たちの事業が日本の出版界に受け入れられるのか、不安がなかったといえば嘘になる。
でも私たちはどこか楽天的だったし、何よりエネルギーだけはあった。イギリスにユン・チアンやJ・K・ローリングがいて、日本にいないはずがない。当時はあまり仕事がなかったので、二人で毎日のようにそんなディスカッションを朝から晩までしていた。
私は「作家のエージェント」システムが、もっと日本に根づいてほしいと思った。欧米では、その存在は常識といってよい。作家にはほとんどの場合、エージェントがついている。同じことが日本でも実現すれば、日本の出版界はもっと面白くなるはずだ。
海外のブックフェアでもっとも輝き、エネルギッシュだったのは、コンテンツをコントロールしている「作家のエージェント」だった。彼らがどんどん仕掛けて話題を作っていたのだ。
日本でも同じような状況を作ることができれば、新しい作家、新しいコンテンツが次々と生まれるに違いない。そうなれば長期低落傾向にあると言われる出版界も、きっと息を吹き返すはずだ。
景色が変わると、新しい世界の扉が開かれる
そんな思いで始めた作家のエージェント会社だが、ようやく14年が経った。やっていることは当初から変わらず、毎日ひたすら面白い企画について考えている。著者と一緒に企画を練り上げ、出版社の方に会ってはその企画を売り込んでいる。
毎年数人の新人作家のデビューに関わっているが、著者デビューを果たした作家からよく言われるのが、「毎日見慣れた風景でも、本を出すと、違った風景に見える」ということだ。
個人差はあると思うが、それにはふたつの意味がある。
ひとつ目は、本を書くことが決まった段階。ビジネス・実用書のジャンルであれば、多くの場合、出版社の会議で企画書が通ったと編集者から連絡がくるだろう。そうすると、作家はそれまでよりも耳をそばだて、目を見開くようになる。無意識に、これから書くコンテンツの肥やしになるものはないものかと、それまで以上に高感度なアンテナを張り巡らすようになるというのだ。
ふたつ目は、自分で書いた本が世に出た後のことである。自らのコンテンツが世の中からどのような反応を受けるのか、世間が変わったのではないかと、周囲に気を配るようになるというのだ。これまでは何気なく通っていた書店でも、本を出してからは、自分たちの本が並んでいるかどうか必ずチェックする。インターネットで何か検索するときも、ついつい自分たちの書籍を読んだ人の感想をチェックする。
本を出すことが面白いのは、ただ日常の風景の見え方が変わるだけにはとどまらず、これまでとは違った世界を切り開く可能性を持っていることだ。
たとえば、弊社所属作家に奥野宣之さんという人がいる。編集・ライター志望者向けのセミナーに呼ばれて講義をしたときに出会ったのだが、提出してきた企画書が面白かったので声をかけた。独自の情報整理術を公開した『情報は1冊のノートにまとめなさい』でデビューし、シリーズ3部作は50万部のベストセラーとなり、これまですでに10冊以上の著書を出されている。
もともと業界紙の記者をしていて、かなり知識欲の強い人ではあるが、本を書くうちに図書館についての興味が増したらしく、とうとう司書資格まで取ったのだという。そして今回、「できるビジネスマンになるためには、いかに図書館を使い倒すか」を書いた本まで出してしまった(『図書館「超」活用術―最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける』)。ここまでできる人はそうはいないが、著者になるということは、読者でいたときとはまったく別の世界に住むことになるということなのだ。
「作家のエージェント」として、私が目指すもの
出版はコンテンツビジネスだ。作家がコンテンツを作り、出版社がそれを本という形にして世に広める。良質のコンテンツを生むのは「個の力」。そしてそれを普及させるのは出版社の「組織力」。私たち作家のエージェントは、この二つにガッチリと手を組ませて、勝利の方程式を完成させる存在だ。
日本の出版界は長い不況にあえいでいる。だけどこれはチャンスなのだ。うまくいっていないからこそ、新しい発想、新しいやり方が求められる。結果を出せばそれが評価され、定着する。常識が変わり、時代が変わるのだ。「不況」は、「変われ!」というシグナルなのだ。
それだけではない。さまざまな技術革新で世界は急速に狭くなっている。今や出版界にとってもマーケットは日本だけじゃない。世界だ。
今、出版界は思う存分自分の力を試すことができる時代に突入している。間違いない。考えただけでワクワクする。




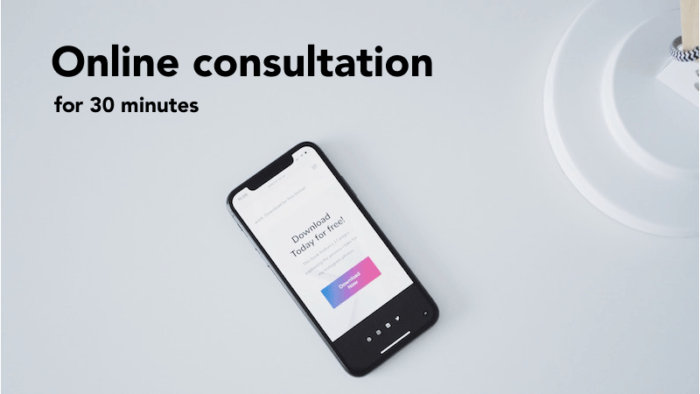



 1
1