ゴーヤを手に取ると、ゴジラに見えてしまう。包丁で縦に切ってみて、種が真っ赤に熟れていると、”蒲田くん”を思い出して嬉しくなってしまう。
シン・ゴジラ観た?ではなく、何回観た?と聞かれるこの頃。
そんなゴジラの音楽を作った作曲家が、実は今でも日本のクラシック音楽界に多大な影響を与え続けていることをご存知だろうか。
ゴジラ ゴジラ ゴジラゴジラゴジラ
ゴジラの音楽として最も有名なテーマといえば、「でで でん・でで でん・でででで でででで でん」という変拍子が印象的な楽曲である。
ゴジラを観たことがない人でもこの曲だけは聞いたことがあるのではないだろうか。
伊福部昭作曲のこのゴジラのテーマは、初代のゴジラ映画(1954年)に使用され、シン・ゴジラにもオリジナルのモノラル音源のまま採用されている。
これを聞いただけで、ゴジラの存在感が増幅される。
言い方は悪いが怪獣の着ぐるみが歩いているだけの映像に、この音楽によって雄々しさ、気高さ、恐怖、そして神々しさが付加されるのだ。
さらには、この「でで でん」の部分に「ゴジ ラ ゴジ ラ ゴジラゴジラゴジ ラ」と、頭の中で勝手に歌詞をつけてしまう現象がおこる。
もうこれは、今やゴジラでしかない。素晴らしい楽曲である。
ゴジラとラヴェル
そんなゴジラのテーマには、実はクラシック音楽の元ネタがある。
ゴジラのテーマを作曲した伊福部昭は、自身が尊敬しているフランスの作曲家モーリス・ラヴェルの「ピアノ協奏曲 ト長調」(1931年)の第三楽章に登場する変拍子の部分から着想し、楽曲に組み入れた。
1944年に伊福部昭によって作曲された「管弦楽の為めの音詩 寒帯林 第三楽章 山神酒祭樂」の終盤に、今のゴジラのテーマに近い旋律が登場した。
その後伊福部は、自作品の中で何度もこの旋律を用いたのち、ようやくゴジラのテーマへと辿り着いている。
3度の下降(ドシラと音が下がっていく部分)と変拍子というモチーフが、よもや日本の特撮映画で怪獣のテーマとして使われるとは、ラヴェルも想像だにしていなかっただろうが、ラベル自身もまた、この「ピアノ協奏曲 ト長調」を作る際に、「モーツアルトやサン=サーンスと同じような美意識を持って作曲した」と語っている。
作曲家にとっての先達の轍といったところであろうか。
ゴジラと聖書
伊福部昭は、ゴジラをはじめとする多数の映画音楽のために、一般的には商業作曲家のイメージが強い。
しかし実は、日本のクラシック音楽教育に大いに貢献した作曲家である。
特にその著書『管弦楽法』は「聖書」という単語を用いて常に語られている。
作曲や指揮を目指す人にとっては、この本がまるで聖書のように重みがあるという意味である。
上下二巻による分厚いこの本は、管楽器、弦楽器の仕様や音色効果はもとより、音響効果や心理的効果についても言及されており、実践的なアドヴァイスまでを網羅した音楽的知識の集大成本となっている。
西洋の楽器で西洋の楽典にのっとって生み出される音楽に関して、日本人である伊福部昭があの時代に日本語でこの『管弦楽法』を書いた功績は計り知れない。
膨大な作曲知識と理論を持った伊福部昭に師事していなければ、その後の日本の音楽界を牽引した作曲家、芥川也寸志や黛俊朗は生まれなかったかもしれない。
伊福部がいなければ、今に連綿と続く日本における音楽教育や音楽史もまた、違ったものになっていただろう。
音楽家のそばにいるということ
たかが昭和の特撮映画の元ネタありの音楽だと、伊福部昭の音楽を軽んじることは簡単だろう。
しかしよくよく知ると、そこには伊福部の音楽への深い知識と経験、そして畏敬の念があることがわかる。
そしてそんな楽曲を演奏してきた演奏家がいる。伊福部の聖書を学んできた多くの作曲家や指揮者がいる。
ゴジラを見ているだけでは分からない、音楽の深く難しい世界が今もここにあるのだ。
私は音楽のことは何もわからない。
作曲の苦悩も、演奏技術を上げるための努力がどれほど大変なことなのかも。音楽家ではない私には。
だからこそ私は、「ただ単に批判するだけの人」にはなるまいと、音楽家のそばにいることに決めた時に誓った。
どんな音楽にも、それを作った人の歴史があり、演奏者の努力がある。
これまでこの連載の中で、いつもそんな音楽家のそばに寄り添ったものを書いてきたつもりだ。
演奏家が自分の理想を現実に落とし込む”事始め”としてのCD製作支援について書いた。
演奏家のこと、絶対音感のこと、そして夫の作曲風景のことにも触れた。それらに多くの反響をいただいて感謝している。
そしてこれまでの文章の中に、私の音楽への愛情を汲み取っていただけたとしたら幸いである。
そしてこの連載のおかげで、私自身が「自分の作品を人にさらす」ことの怖さも知った。
作曲家や演奏家が、常に「批判対象にもされる」という覚悟を持っているのだと実感することもできた。
これは今後私が仕事をしていく上での大きな財産になるだろう。
音楽家のそばにいるということは、私にとって何より価値のある幸福だと、最後に心を込めて記したい。
そしてそんな音楽家が作り出した幸福は、あなたのそばにも、いつも、あるのだ。

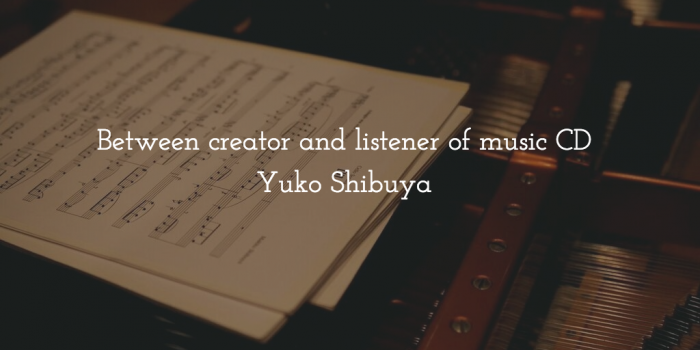


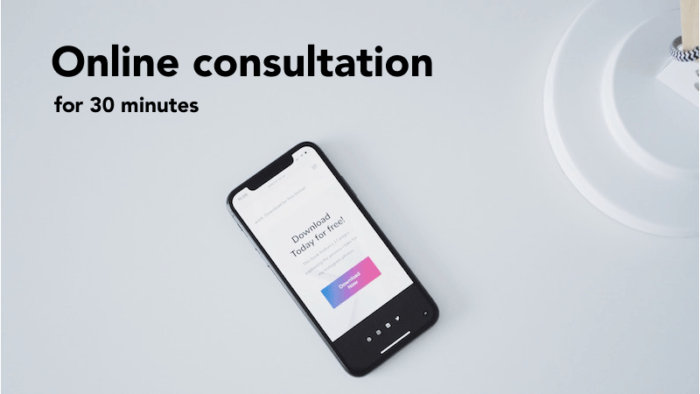


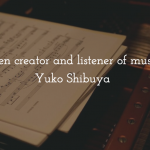
 12
12